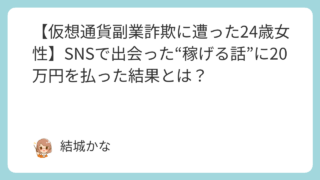 詐欺被害の体験談
詐欺被害の体験談 【仮想通貨副業詐欺に遭った24歳女性💰】SNSで出会った“稼げる話”に20万円を払った結果とは?
今回は、“初心者でもできる仮想通貨の副業”という話に誘われて、気づいたら20万円を運営費名目で失っていたという、森優奈さん(仮名・現在29歳/当時24歳)の体験談をご紹介します💸仮想通貨という言葉の響きに希望を抱き、SNSで見つけた「自動運...
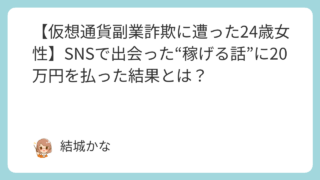 詐欺被害の体験談
詐欺被害の体験談 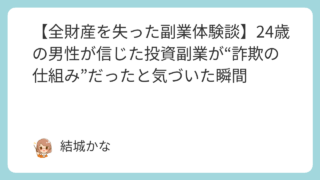 詐欺被害の体験談
詐欺被害の体験談 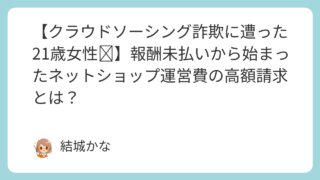 詐欺被害の体験談
詐欺被害の体験談 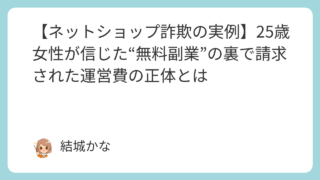 詐欺被害の体験談
詐欺被害の体験談 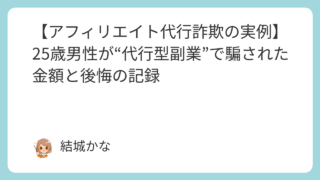 詐欺被害の体験談
詐欺被害の体験談 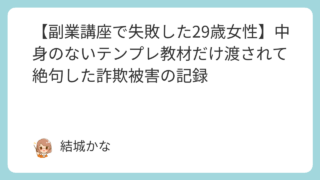 詐欺被害の体験談
詐欺被害の体験談